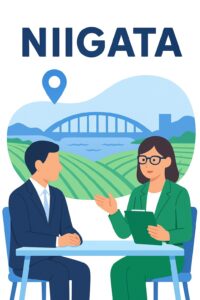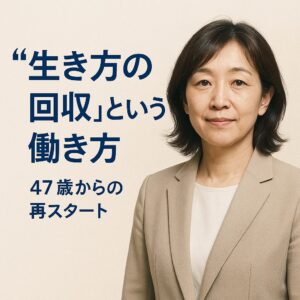【建設業・運送業向け】労災対応の実務ポイントと防止策|最新データを新潟の社労士が解説
令和6年の労働災害は、死亡者数746人と過去最少を記録した一方で、休業4日以上の死傷者数は135,718人と4年連続で増加しました。
中でも建設業の死亡者は232人(前年比4%増)、**陸上貨物運送事業の死傷者は16,292人(前年比0.5%増)**と依然として高水準です。(厚生労働省「令和6年労働災害発生状況」より)
建設業・運送業は、墜落・転落や交通事故など重大災害のリスクが高い業種。この記事では、最新統計を踏まえた現場の労災リスクと初動対応、再発防止策を、新潟の社労士が解説します。
建設業の労災リスクと初動対応
よくある事故と背景
墜落・転落:死亡188人(前年比7.8%減)と依然最多 重機による挟まれ・巻き込まれ 高齢作業員や外国人労働者の増加による安全教育不足
初動対応の基本
救急要請・応急処置 現場保存・監督署へ報告(労働安全衛生法第100条) 労災保険の申請(療養補償給付・休業補償給付)
国は「第14次労働災害防止計画」で令和9年までに建設業の死亡者を15%以上減少させる目標を掲げています。
2運送業(陸上貨物運送事業)の労災リスクと初動対応
よくある事故
交通事故(道路):死亡123人(前年比16.9%減) 荷積み・荷下ろし時の転倒や腰痛 長時間労働による過労・睡眠不足
初動対応の基本
交通事故の場合、第三者行為災害として警察・監督署への報告が必要 被災労働者の療養補償、休業補償の請求 加害者がいる場合は損害賠償保険との調整
国は令和9年までに陸上貨物運送事業の死傷者数を5%以上減少させることを目標にしています。
3.労災申請の流れと必要書類
健康保険は使用できないので、労災専用の様式が必要になります。様式5号や療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 休業補償給付支給請求書(様式第8号) 事業主の証明と監督署提出が必須です。
オンライン申請(e-Gov)も可能ですが、医師の証明も必要なので、まだ紙で対応が原則です。入力不備や証明の不備による差し戻しが多く、社労士のサポートが有効です。
4.再発防止のために企業ができること
定期的な安全教育とKY(危険予知)活動 ヘルメット・安全帯の使用徹底、現場巡視 長時間労働の是正と健康診断 運転前後のアルコールチェック・点呼記録の徹底
高年齢労働者や外国人労働者の増加に対応した教育が、今後の安全対策の鍵になります。
5.社労士に相談するメリット
複雑な申請書類の作成・監督署対応を代行 会社のリスク管理体制(安全衛生規程、就業規則)を整備 助成金の活用(安全対策設備導入や働き方改善の助成金)
社労士は「事故後の手続き」だけでなく、事故を未然に防ぐ体制づくりにも伴走します。
まとめ/安全管理は「経営課題」!
建設業・運送業は、令和6年も依然として労災が多い高リスク業種です。
国の中期計画では死亡災害・死傷者数の削減目標が定められており、安全管理は企業経営の最重要課題といえます。
こもれび社労士事務所では、
労災申請の手続き 安全衛生規程や就業規則の見直し e-Gov申請や監督署対応
をワンストップでサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。
https://komorebi-sharoushi.com/rousai/
内部リンク推奨箇所
既存記事「第三者行為災害とは?」 「労災給付の種類まとめ」 「労務DXで人手不足を補う方法」
参考・出典
厚生労働省「令和6年労働災害発生状況」 https://www.mhlw.go.jp/
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。