税理士が無資格で社労士業務を行った社労士法違反のニュースから学ぶ:資格の重みと、安心して選ばれる社労士でいるために
2025年10月、日本経済新聞(記事リンクはこちら)などの報道によると、税理士が社会保険労務士法違反の疑いで逮捕されました。
他士業が社労士業務を無資格で請け負ったとして摘発されるケースは珍しく、士業全体にとっても大きな教訓となる出来事です。
私自身、同じ専門職としてこのニュースに触れ、「資格の重み」と「誠実に業務を行う責任」を改めて感じました。
なにが問題なのか(概要)
社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令に関する手続きや相談・指導を業として行う専門職です。これらの業務は法律で範囲が定められており、有償で行うには社労士資格が必要です。仮に他資格(例:税理士・行政書士など)を保有していても、社労士の独占業務を無資格のまま有償で請け負うと法令違反となる可能性があります。
ポイント:
・「誰がやってもよい一般事務」と「社労士にしかできない業務」は明確に線引きされている。
・“代行してほしい”というニーズがあっても、法の枠内で対応することが必須。
なぜ起こるのか(背景の3要因)
- 資格間の誤解/責任意識の不足
「この程度なら対応できる」という思い込みが、独占業務への越境を招くことがあります。 - 顧客ニーズとのズレ
ワンストップを求める依頼に応える過程で、表示や契約が曖昧になり、結果として法令違反の構図に。 - 価格・効率プレッシャー
手続きの「簡便性」に目を奪われると、資格の重みや職責が軽視されやすくなります。
社労士としての備え:信頼をつくる3ステップ
① 専門領域の明示と適切な表示
サイトやLP、名刺・提案書に登録番号・専門領域を明記。当事務所のトップページでも、労務DX・労災・障害年金を柱として示しています。
② プロセスと料金の透明化
「社労士が行う手続き」「他資格や一般事務との違い」を明文化。対応範囲・料金・納期を事前に共有し、誤認を防ぎます。関連:料金と導入の目安
③ DXで事務を軽くし、“人”に時間を振り向ける
クラウドやAIで定型業務を効率化し、相談・判断・合意形成といった「人にしかできない価値」に集中します。労務DXの全体像はこちらをご参照ください。
企業・個人の方へ:任せ先を選ぶチェックリスト
- 資格表示・登録番号が明記されているか
- 得意分野(労務DX/労災/障害年金など)が具体的に示されているか
- 手続きの流れ・費用・納期が事前に説明されるか
- 問い合わせ後、状況を丁寧にヒアリングしてくれるか
- 必要に応じて他士業と連携し、法の枠内で対応してくれるか
障害年金のサポート概要はこちらのページに整理しています。
よくある質問(簡易版)
Q. 税理士や行政書士に相談しても良いの?
A. 分野ごとに独占業務があります。労働・社会保険の手続きや相談・指導は社労士の専門領域です。必要に応じ、士業間で適切に連携します。
Q. どこまでが「社労士でないとできない業務」?
A. 労働・社会保険諸法令に関する書類の作成・提出代行・相談/指導などは社労士の業務とされます。個別案件では事前にご説明します。
Q. まず何を準備して相談すれば良い?
A. 現在のご状況(会社・ご本人)、課題(例:就業規則・労災・傷病手当金・障害年金)を箇条書きでOK。必要書類は対話の中で一緒に整えます。
まとめ:資格の重みを胸に、誠実に
士業の価値は、書類の作成スピードだけでは計れません。制度と現場、人と法律をつなぐ翻訳者として、そして何より「安心して任せられる存在」として、法の枠内で誠実に向き合う——それが社労士の基本姿勢だと考えています。
📘 続編はこちら: 税理士が社会保険手続きを代行するのは違反?|無料でも社労士法に抵触する線引き
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。

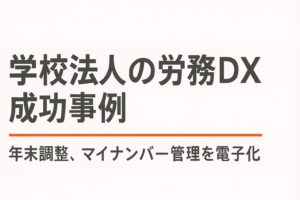

“税理士が無資格で社労士業務を行った社労士法違反のニュースから学ぶ:資格の重みと、安心して選ばれる社労士でいるために” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。