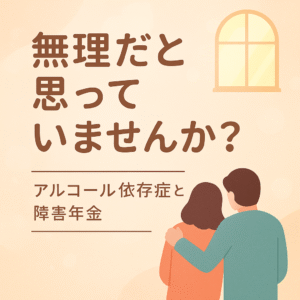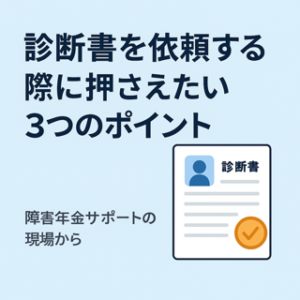【社労士解説】発達障害と障害年金|初診日と認定日の違いをわかりやすく説明
発達障害で生活や就労に困難がある場合、障害年金を受けられる可能性があります。
ただし、申請にあたってとても重要なのが 「初診日」と「認定日」 です。
この2つの意味を誤解している方は多く、手続きを進めるうえで大きな壁になりやすい部分です。この記事では、初診日と認定日の違いについて、社労士の視点から整理します。
発達障害と障害年金の対象
自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)なども、日常生活や就労に支障がある場合は障害年金の対象となります。
ここで大切なのは「診断名」ではなく、生活や社会参加にどれだけ困難さがあるか です。
初診日とは?
初診日とは、発達障害と診断された日ではなく、はじめて医療機関を受診した日 を指します。
具体例
子どもの頃に「落ち着きがない」と小児科を受診した日 大人になってから初めて心療内科を受診した日
このように、医師が症状を記録した日が「初診日」になります。
👉 初診日が 20歳前か20歳以降か で、障害基礎年金か障害厚生年金かが分かれます。
認定日とは?
認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日をいいます。
この認定日の時点での障害の程度に基づいて、障害年金の等級(1級・2級・3級)が決まります。
初診日と認定日が重要な理由
年金の種類を分ける基準になる 初診日が20歳前なら「障害基礎年金」 初診日が20歳以降で厚生年金加入中なら「障害厚生年金」 等級認定のタイミングになる 認定日時点の症状で障害の程度が判断される その後も症状が変化すれば、更新や再認定の対象になる
まとめ
初診日 = 最初に病院へ行った日(診断日ではない) 認定日 = 初診日から1年半後に障害の程度を判断する日
障害年金の申請では、この2つの日付を正しく押さえることが大切です。
発達障害の方にとっても、制度を理解し活用することが安心につながります。
障害年金の手続きは複雑ですが、制度を正しく理解することが大きな安心につながります。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。