税理士が社会保険手続きを代行するのは違反?|無料でも社労士法に抵触する線引き

「無料なら大丈夫?」と迷ったときに知っておきたい社労士法の考え方
前回の記事(税理士が無資格で社労士業務を行った社労士法違反のニュースから学ぶ:資格の重みと、安心して選ばれる社労士でいるために)では、他士業による社労士法違反の事例を取り上げました。
記事の公開後、読者の方からこんなご質問をいただきました。
「顧問税理士に、社会保険や雇用保険の手続きを無料でお願いしています。
このような場合も社労士法違反になるのでしょうか?」
とても鋭いご質問です。
実はこの「無料なら大丈夫?」という点は、現場でも誤解されやすいグレーゾーンです。
今回は、全国社会保険労務士会連合会の令和6年度「職業倫理テキスト」も踏まえて、
この線引きをわかりやすく解説します。
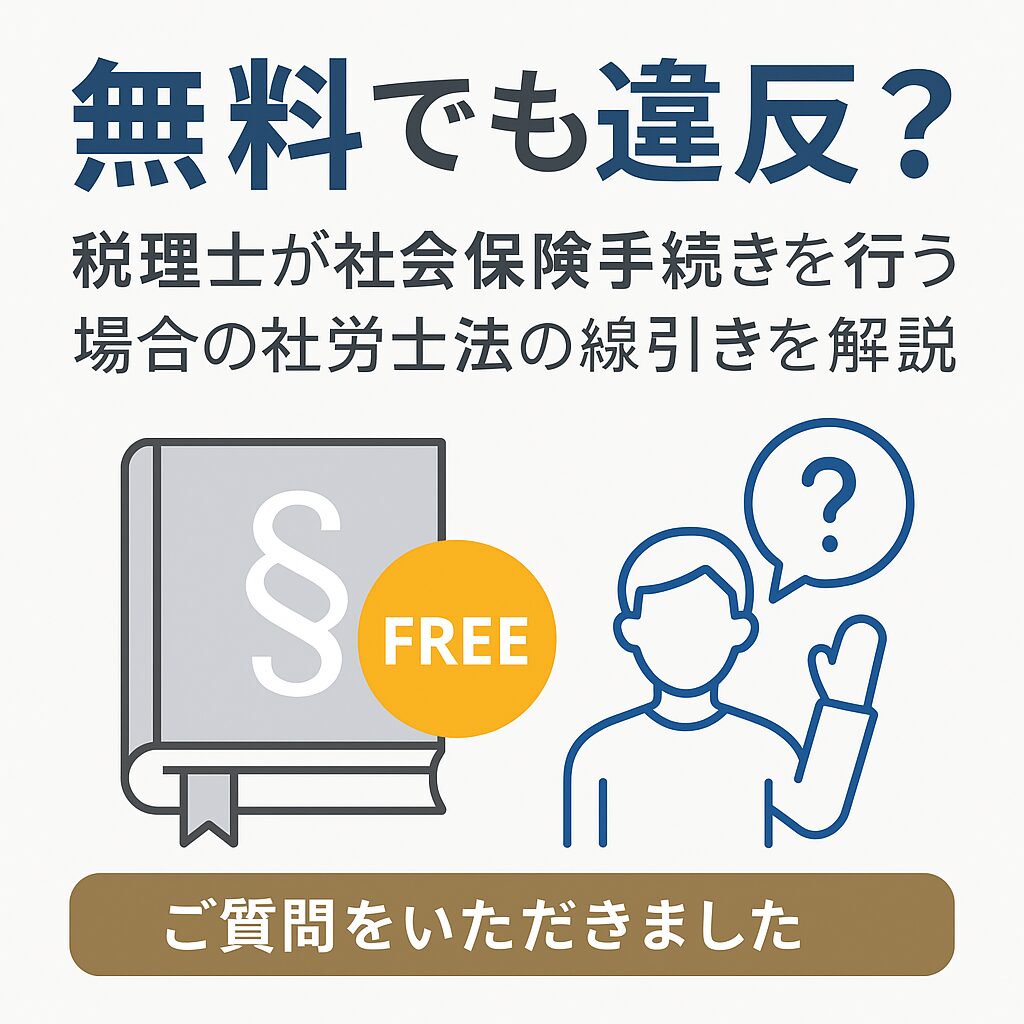
要点:① 社会保険等の手続代行は社労士の独占業務/② 形式上「無料」でも顧問料内包や継続提供は違反の可能性/③ 依頼側に直罰は通常なしだが、幇助リスクや実務上の損失に注意
社会保険手続きは社労士の独占業務
社会保険労務士法第2条では、社会保険・雇用保険・労働保険などの手続き代行を、
「報酬を得て業として行うこと」が社労士の独占業務であると明記しています。
つまり、これらの手続きは原則として社労士しか代行できません。
税理士や行政書士など、他資格者であっても、社労士登録をしていなければ代行はできない仕組みです。
無料でも違反になるケースがある理由
「報酬を得て」という文言を文字どおり“有料か無料か”とだけ捉えるのは危険です。
実務上は、次のようなケースでは形式上無料でも違反と判断される可能性があります。
- 顧問料の中に手続業務が実質的に含まれている
- 継続的・定期的に他士業が代行している
- 顧問契約の「付帯サービス」として手続きを行っている
このような場合、「報酬に含まれている」と見なされるため、
形式上は無料でも実質的には社労士法違反になる可能性が高いのです。
職業倫理テキストで明示されている「他士業との線引き」
全国社会保険労務士会連合会の令和6年度「職業倫理テキスト」第VII章には、
次のように明記されています。
「社労士業務は社労士本人と顧客が直接契約を結ばなければならず、
他士業の名義で一括して受託することは違反にあたる。」
つまり、たとえ他士業が顧問契約を結んでいたとしても、
社会保険や労働保険の代行は「社労士本人の直接契約」でなければなりません。
また、他士業やコンサル会社名義での再委託・一括受託も、社労士法第27条(業務の制限)に抵触します。
違反にならない場合の目安
一方で、次のようなケースは直ちに違反とはなりません。
- 単発的・好意的な対応(例:様式の見本を見せる程度)
- 報酬性・継続性のない範囲にとどまる場合
ただし、これらも繰り返されると「実質的な業務」とみなされるおそれがあります。
境界線は解釈に幅があるため、慎重な判断が求められます。
社労士法違反の罰則と発覚のきっかけ
社会保険労務士法では、無資格で独占業務を行った場合に刑事罰が定められています。
具体的には、第32条の2(罰則)第1項第6号に基づき、
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
また、法人等が関与していた場合は両罰規定(第36条)により、法人自体にも罰金刑が科されることがあります。
根拠条文(抜粋)を表示
・社会保険労務士法 第2条(業務)…「報酬を得て業として行う」手続代行は社労士の業務
・同法 第27条(業務の制限)…名義貸し・不適切な再委託の禁止
・同法 第32条の2(罰則)…無資格業務は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」等
・同法 第36条(両罰規定)…法人関与時の法人処罰
社労士法違反はどのようにして発覚するのか?
発覚のきっかけとして多いのは、次のようなケースです。
- 顧客や元顧客が「誰が手続きをしたのか」を確認し、無資格と判明
- 同業者や他士業からの情報提供(広告・HPの越権表示など)
- 役所側の電子申請データで、委任状やアカウント名義の不一致を検知
- 調査時に帳票・請求書・契約書から無資格業務が明らかになる
- 内部スタッフからの通報や証拠提供
特に電子申請や顧問契約の内容は記録が残るため、「誰の名義で」「どこまでの範囲で」業務を行ったかが後から確認されやすくなっています。
このため、社労士以外の名義で社会保険や労働保険の手続きを継続的に行うことは、リスクが非常に高い行為といえます。
こうした違反は、悪意よりも「知らなかった」「少しのつもりだった」というケースが多く、
日頃から法令と倫理の両面で線引きを意識しておくことが大切です。
法令と倫理の両面から、「契約の名義」「業務範囲」「報酬関係」を明確にしておくことが重要です。
無資格者に依頼した側は罰せられるのか?
社会保険労務士法の罰則は、原則として「無資格で業として社労士業務を行った側」に科されます。
依頼した企業や個人に対して、直接の刑事罰が科されることは通常ありません。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
- 無資格であることを知りながら継続的に依頼していた場合
- 違法な業務を指示・幇助したと評価される行為があった場合
このようなケースでは、刑法上の「幇助・教唆」に問われる可能性があり、行政からの指導対象となることもあります。
また、手続きの差し戻しや給付遅延、顧客情報管理の不備など、実務上のリスクも大きいため注意が必要です。
安心して社労士に依頼するために
社会保険・労働保険の手続きは、専門資格を持つ社会保険労務士が「本人名義」で行うことが法律上のルールです。
無料・サービスの一環などの名目でも、報酬性や継続性があれば社労士法違反に該当するおそれがあります。
こもれび社労士事務所では、法令と倫理に基づいた透明な契約と安全な手続きを行っています。
「この委託方法は大丈夫?」「税理士との線引きを整理したい」などのご相談も、初回無料で承っています。
社労士法違反を見つけたときの通報・相談ルート(まとめ)
まずは 都道府県の社会保険労務士会 への通報が現実的な一次窓口です。悪質・反復的な場合は、労働局や警察へと段階的に進むことがあります。
① 都道府県社会保険労務士会(例:新潟県社会保険労務士会)
└ 無資格業務/名義貸し/他士業の越権などの情報提供窓口
↓(悪質・反復性が高い等)
② 行政(厚生労働省・地方労働局)
└ 行政的な照会・指導、電子申請の名義不一致の確認など
↓(刑事罰の対象となる場合)
③ 警察・検察
└ 社労士法違反(第32条の2 等)として捜査・告発・起訴の対象
通報時にあると良い情報
- 誰が・いつ・どの手続きを行ったか(メールや見積/請求書、委任状、契約書の写し)
- 電子申請の提出者名義・ID・タイムスタンプ等の画面や控え
- HP/チラシ等での越権表示のスクリーンショット
※通報は匿名でも可能ですが、事実が確認できる資料があるとスムーズです。まずは最寄りの社労士会事務局に状況を相談してください。
※補足:
本記事は「通報を勧める」ことが目的ではありません。
多くの場合、問題は通報の前に「線引きを整理する」ことで解決できます。
まとめ|法令と倫理の両面で透明な関係を
無料だから大丈夫、という思い込みは危険です。
「報酬性」と「継続性」があれば、たとえ形式上無料でも社労士法違反とみなされることがあります。
他士業との連携こそ、法令・倫理に基づいた正しい線引きが大切です。
資格を持つ者として、正しい線引きと誠実な対応を続けていくことが、
お客様の安心と業界全体の信頼につながると感じています。
本記事が、他士業との連携や法令遵守に関心をお持ちの方の参考になれば幸いです。
こもれび社労士事務所では、法令と倫理に基づく安心の労務サポートを心がけています。
必要に応じて、当事務所でも「線引きの整理」や「適法な役割分担」のご相談をお受けしています。
まずは現状チェックから👇
チェックリスト(PDF・1枚)を無料ダウンロード※社内配布可・改変不可/最新版: 2025-10-30
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。



“税理士が社会保険手続きを代行するのは違反?|無料でも社労士法に抵触する線引き” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。