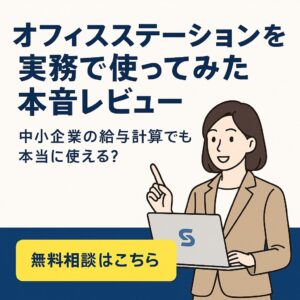社労士が“建設仮勘定”でつまずいた話|知らなかった会計処理の落とし穴と学び
社労士が“建設仮勘定”でつまずいた話|知らなかった会計処理の落とし穴と学び
開業してから少しずつ、経理や会計の実務にも向き合うようになりました。
社労士として労務や年金を扱うのは慣れていても、「建設仮勘定」という言葉を初めて見たときは正直ピンと来ませんでした。
でも、不動産を所有している方や新築・改修を行う事業者さんにとって、この「建設仮勘定」は節税や修正申告にも関わる重要な考え方なんですね。
1.最初は「経費にしておけばいい」と思っていた
自分の法人で不動産を持ち、工事費用や登記費用などが発生したとき、最初はすべて経費で処理していました。
登記の司法書士報酬や登録免許税、印紙代まで「支払手数料」「租税公課」として入力していたのです。
ところが、試算表を見直していて気づきました。
「あれ? これって建物がまだ完成していない時期の支出じゃないか?」と。
そこで知ったのが「建設仮勘定」という存在です。
2.建設仮勘定とは?
簡単に言うと、建物や構築物が完成するまでの支払いを一時的にまとめておく“資産の箱”のようなものです。
完成後に「建物」や「構築物」として振り替え、そこから減価償却が始まります。
だから、登記費用や中間金、完成前の利息などは経費ではなく建設仮勘定に入れる必要があります。
逆に、融資契約の印紙や保証料のように借入に直接関係する費用は経費でOKです。
3.弥生会計での修正と気づき
私は弥生会計オンラインを使っています。修正時は以下のような流れで進めました。
- ① 「建設仮勘定」を固定資産科目として追加
- ② 前渡金(中間金など)を建設仮勘定へ振替
- ③ 登記費用・印紙代・完成前利息も建設仮勘定へ振替
- ④ 建物完成日に「建設仮勘定 → 建物」へ振替
この修正で、決算の赤字額も変わりました。 結果として、より正確な帳簿に整えることができたと思います。
4.学び:「知らないことを放置しない」
社労士は労務・年金の専門家ですが、経営者や不動産オーナーに関わるとき、会計や税務の知識も不可欠だと痛感しました。
「これは経費でいいのか?」と迷ったとき、少し立ち止まって調べるだけで、後から大きな修正を避けられます。
税理士さんや会計士さんに確認しながら進めるのがいちばん安全です。
そして、士業同士で支え合える関係があると心強いですね。
5.まとめとメッセージ
- 建設仮勘定は「完成前の支出」を一時的にまとめる資産
- 登記・印紙・完成前利息は建設仮勘定に含める
- 経費処理のままにすると、利益や減価償却の計算にズレが生じる
もし同じように悩んでいる方がいたら、「知らなかった」で終わらせず、丁寧に修正することが大切です。
📩 ご相談のご案内
こもれび社労士事務所では、労務DXの導入支援を中心に、会計まわりの初期設計や帳簿の整理などもサポートしています。
弥生会計を使っていて「この処理で合ってる?」というお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。