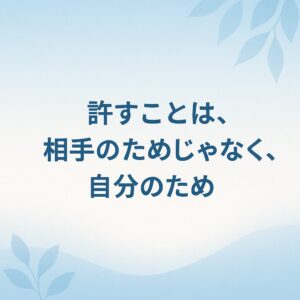「コロハラ」を職場で起こさないために――社労士が整理する感染症と労務管理
家族が陽性でも本人が無症状なら登校・出勤を可とする運用が広がる一方で、現場では 「念のため休んでほしい」「陰性証明を出して」など、感情と科学が衝突しやすい局面が残っています。 本稿では、労務管理の観点から“コロハラ(コロナハラスメント)”を防ぐ実務ポイントをまとめます。
現場では「正しさ」よりも「印象」や「不安」が先に立ち、 本人よりも“周囲の声”で判断が左右される場面も少なくありません。 そんなときこそ、社労士が示す“ルールの安心”が求められます。
1. コロハラ(コロナハラスメント)とは
感染者やその家族、濃厚接触歴がある従業員に対して、根拠の薄い忌避・非難・不利益取扱いを行うことの総称です。 具体例は以下の通り。
- 家族が陽性というだけで出勤停止・配置転換・昇給据え置きを求める
- 復職時に「空気を読んで来ないで」といった同調圧力や陰口がある
- 私的な行動(買い物・送迎など)への過度な干渉や詮索
これらは、職場環境配慮義務やハラスメント防止の枠組みに抵触するおそれがあり、労務リスク(離職・紛争・労基署/労働局対応)を生みます。
2. まず押さえる原則(社内で合意しておくべき土台)
- 科学的・制度的根拠に基づく判断…自治体や医療の最新指針をベースに、会社の運用を明文化。
- 私的評価・噂を運用に持ち込まない…「不安だから」という理由だけで不利益取扱いをしない。
- 本人のプライバシー配慮…体調・検査結果・家族状況は目的外共有をしない。
- 代替手段の用意…在宅勤務・時差出勤・有休/特別休暇など複線化で実害を最小化。
3. 就業規則・社内ルールに入れるべき項目
3-1. 出勤可否の判断フロー(雛形)
- 本人に発熱・咳・咽頭痛等の症状がある → 出勤見合わせ(医療機関受診/自宅静養)。
- 本人は無症状だが家族が陽性 →
- 会社の方針:在宅勤務推奨。職務上出社が必要な場合は、体温・体調セルフチェック+感染対策を徹底。
- 検査の要否は地域や産業特性を踏まえ、方針で明示(必要な場合は市販キット可/医療機関推奨など)。
- 本人が陽性 → 保健・医療の指示に従い出勤停止。復職は症状軽快と業務安全性を基準に判断。
現場で曖昧なまま運用すると、「あの部署は出勤OK」「うちはNG」といった 不公平感や不信感につながります。 トラブルを防ぐには、就業規則・社内ルールに“線を引く”ことが第一歩です。
3-2. 社内周知テンプレ(社内ポータル/全社メール例)
感染症に関する出勤基準は、最新の公的ガイドラインに基づき定めています。
不安やご意見がある場合でも、個人に対する圧力・詮索・噂の拡散は厳に慎んでください。
運用上の判断は人事・産業医が行います。疑問点は所属長または人事にご相談ください。
3-3. 規程への明文化サンプル(抜粋)
【感染症対応規程(抜粋)】
第X条(出勤可否)
1 本人に発熱等の症状がある場合は出勤を見合わせ、上長へ連絡のうえ医療機関の受診等を行う。
2 本人が無症状で家族が陽性となった場合は、在宅勤務を基本とし、職務上やむを得ず出社する際は
体温・症状の自己申告、マスク着用、手指衛生、換気等の対策を徹底する。
3 検査の実施は公的指針・職務特性を勘案して会社が定める。市販キットの結果をもって足りる場合がある。
4 復職は、症状の軽快及び業務上の安全が確保されたと人事が判断したときとする。
第Y条(ハラスメントの禁止)
1 感染症又はその疑いを理由とする不当な言動、詮索、情報拡散、出勤妨害等を禁止する。
2 前項に抵触する行為があった場合、就業規則に基づき懲戒の対象とする。
4. 実務運用チェックリスト
- 最新の社内基準を1ページに集約し、誰でも見られる場所に掲載している
- 上長・現場リーダー向けに「言ってはいけない言葉」例を教育(例:「空気読んで休んで」など)
- 体調申告フォーム(体温・症状)を用意し、紙・口頭依存を回避
- 在宅・特別休暇・シフト振替などの代替オプションを整備
- 相談窓口(人事・産業医・外部相談)を明示し、匿名通報も受けられる体制
5. よくある質問(社内から出やすい“もやもや”への回答例)
- Q. 「陰性証明」を必ず提出させるべき?
- A. 一律義務化は過剰になり得ます。感染状況・業務特性・地域医療体制を踏まえ、 必要な場合のみ(対面接客が多い等)に限定し、代替手段(在宅勤務)も提示を。
- Q. 同僚が不安がって出社に反対しています。
- A. 不安の声は尊重しつつ、会社はルールに基づき判断します。不安解消は 情報提供(換気・マスク方針・席配置)と対話で行い、個人攻撃はさせないことが重要です。
- Q. 家族が陽性でも、どうしても出社が必要です。
- A. 体調セルフチェック、短時間立ち寄り、時差出勤、滞在エリア制限など、 リスク低減策をセットで運用します。必要に応じて簡易検査を活用します。
6. まとめ
「本人は陰性なのに休めと言われた」「不安だから来ないでと言われた」 ― こうしたトラブルは、制度よりも“コミュニケーションのずれ”から起きています。 科学と感情の間をどう橋渡しするかが、これからの労務管理の課題です。
感染症をめぐる“正しさ”は状況で揺れます。だからこそ、明文化した社内基準と 代替手段、そしてハラスメントを許さない文化が不可欠です。 感情に左右されない運用は、従業員の安心と事業継続の両方を守ります。
規程整備や運用設計のご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。 現場のリアルと法的枠組みの“ちょうどいい接点”をご一緒に作ります。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

次の一歩を、ここから選べます
迷っていても大丈夫です。いちばん負担の少ない方法からでOK。
※ 個人のご相談(労災・後遺障害・障害年金)/全国対応(LINE・オンライン)
※ 「まず整理だけ」でも大丈夫です