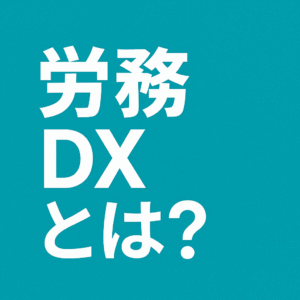労災申請は自分でできる?社労士に頼ってください!
「労災が起きたとき、申請は自分でできるのか?それとも専門家に任せたほうがいいのか?」
現場で事故やケガが起きると、従業員や会社は対応に追われ、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
実際、労災申請は会社や本人でも行えますが、書類の数が多く、記載内容に不備があると再提出や支給の遅延につながるケースが少なくありません。
この記事では、労災申請を自分で行う場合の流れや注意点、そして社労士に依頼するメリットを、新潟で社労士事務所を運営する筆者が解説します。
労災申請は自分でできる?
結論から言うと、労災申請は自分や会社で行うことが可能です。
病院経由等で所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出すれば受理され、給付の審査が進みます。
代表的な書類は以下のとおりです。
様式第5号(労災指定病院に提出)
様式第8号(休業補償給の請求書)
様式第7号(労災指定外やせいこ
ただし、医師の証明や会社の証明が必要になるため、単純に「自分で書けば終わり」というものではありません。
労災申請の基本的な流れ
労災事故発生(通勤災害・業務災害) 医療機関で診断 → 医師に証明を依頼 会社が証明欄を記入 →医師に証明を依頼→病院経由(労災指定病院の療養の場合)等で労基署へ書類を提出 →労基署による審査・問い合わせ対応 給付決定・支給
自分で申請する場合の注意点
書類の記載が難しい 。専門用語や法律に基づく記載が必要な箇所があり、誤記が多い。 提出書類が多い 休業・療養・障害・遺族など給付の種類によって様式が違う。
医師や会社との調整が必須 書類が揃わずに手続きが止まることもある。 期限は原則2年です。第三者行為災害はさらに複雑 交通事故や酔客からの暴力など、加害者が関わるケースは追加書類が必要。
社労士に依頼するメリット
正確な書類作成で再提出リスクを減らせるます。労基署・医師とのやりとりをサポートします。申請から支給までの流れをスムーズに短縮 経営者側も「適切に労災対応をした」と社内アピールが可能です!
👉 筆者はJR東日本グループで労災対応を担当していた経験があり、ほぼ毎日書類を作成したり、各労基署や病院等の対応をおこなってきました。事業所を管轄する労基署が担当になるので、いろんな労基署(県や担当者によって対応が異なることまもありました)鉄道会社では、酔客による暴力などによる「第三者行為災害」も数多く見てきました。第三者が絡むので準備すべき書類も増えます。
現場では「こんなケースも労災になるのか?」という声も本当に多く、労基署に確認しながら経験をつんできましたし、専門的なサポートの必要性を強く感じました。
依頼を検討すべきケース
書類が複数種類にわたる(ケガ+休業+障害+第三者行為など) 会社の人事・総務担当様ですと、そこまで経験ごなかったり、小規模事業所で総務担当者がいない 給付の種類が多岐にわたる 労基署からの問い合わせ対応に不安があるなど社労士を頼っていただけるとありがたいです。
まとめ(相談案内)
労災申請は自分で行うことも可能ですが、書類の様式作成のシステム(e-govでは現実的に難しいです)複雑さや調整の難しさから、社労士に依頼したほうがスムーズに進むケースが多いです。ぜひ、お気軽に頼っていただければと思います。労災・労働保険の経験はかなりありますので、ご安心ください!
労災申請に不安をお持ちの方は、ぜひ「こもれび社労士事務所」までご相談ください。
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。