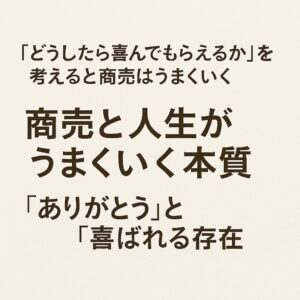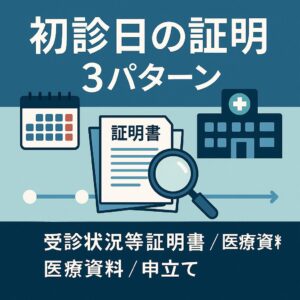就労中でも申請できる?誤解と実際|障害年金の基礎知識と通し方
就労中でも申請は可能。収入がある=自動で不支給、ではありません。 判定は「等級相当の状態像」が基準。就労の有無は補助的事情。 カギは、①初診日 ②保険料納付要件 ③障害認定日/請求時点の状態 の3つ。 就労している場合は、仕事内容・配慮・欠勤状況などの具体を一貫した書類で示すのが通し方のコツ。
よくある誤解と実際
誤解1:「働いていると申請できない/通らない」
実際:働いていても申請・受給は可能。
等級(厚生 1〜3級/基礎 1・2級)は、日常生活能力や労働の制限の程度で判断。
例:短時間・軽作業・配慮多数・欠勤多め → 可能性は十分。 反対に、フルタイム・高難度業務・欠勤ほぼ無・高い成果などは不利になりやすい。
誤解2:「収入が一定額を超えたら一律ダメ」
実際:収入の線引きは制度上なし。ただし“状態像”の推認材料にはなります。
なお、付随する各種助成(非課税判定など)は所得で要件が変わることがあります。
誤解3:「会社にバレるので申請できない」
実際:原則は医療・年金ルートで完結。
ただし、就労状況証明や診断書の整合が必要なケースでは、会社に最低限の事実確認をお願いすることがあります(配慮や欠勤の実態など)。
まず確認する3点(チェックリスト)
初診日 症状で初めて医療機関を受診した日。どの制度(国民年金/厚生年金)で請求するかを決める起点。 保険料納付要件
原則:初診日の前日において、直近1年に未納がない、または加入期間の3分の2以上納付。
障害認定日 or 事後重症
認定日:原則、初診日から1年6か月経過時点の状態。 事後重症:請求時点での状態で判定(遡及はなし)。
※精神・知的・発達のケースは「日常生活能力の判定」や就労状況の具体が重視されます。
就労中の“通し方”4ステップ
① 状態像を具体にそろえる(診断書の核)
●通院頻度/治療内容/症状の波 ●対人・作業・持続・集中・危機回避などの具体的困難 ●家事や金銭管理、服薬管理の援助の要否 ●就労の実際:勤務日数・時間、職務内容、配慮の有無(指示の細分化、配置換え、同僚サポート等)、欠勤/遅刻/早退の頻度
② 記載の“整合性”を担保
診断書・申立書(病歴・就労状況等申立書)・就労状況メモの矛盾をなくす。 「できる/できない」の基準を同じ解像度で書く(例:15分以上の集中がもたない、混雑環境でパニック等)。
③ 就労状況を“配慮つきで可視化”
短時間・軽作業・在宅・ジョブコーチ等の支援がある場合は必ず明記。 病状悪化時の欠勤・離席の取り扱い、実績を数字で。 就労継続支援(A/B型)・移行支援等の利用は“配慮下の就労”として評価材料になります。
④ 会社に依頼する場合の最小限テンプレ
「就労状況の確認書(任意)」
・勤務形態(週◯日◯時間/短時間勤務の合意あり)
・職務内容(分解して記載)
・業務上の配慮(指示の細分化・配置・同行・在宅・負荷軽減 等)
・欠勤/遅刻/中抜けの実績(過去◯か月で◯回)
・評価や指導の頻度(通常より増)
※病名や詳細診療情報は不要。人事情報の最小限共有でOK。
どの等級を狙える?ざっくり目安
厚生3級:就労可能だが職種・配置に著しい制限、欠勤・配慮が常態。 厚生2級/基礎2級:日常生活に著しい制限。就労していても大幅配慮+不安定なら可能性あり。 厚生1級/基礎1級:常時の介助が必要なレベル。就労との両立は基本的に困難。
※あくまで目安。等級は診断書の具体と総合評価で決まります。
申請ルートの選択:認定日請求 or 事後重症
認定日請求(遡及可):1年6か月時点で等級相当なら遡って受給開始も。 事後重症:現在の状態で初めて等級相当 → 請求月の翌月から。
就労中は病状の波が出やすく、“今”が等級相当かを冷静に見極めましょう。
併せて知っておきたい実務
現況届:更新時は状態の変化と就労状況を再確認。 他制度との関係:医療費助成や税の非課税は所得で要件が変化。 メンタル不調の方へ:リワーク/就労移行支援の利用実績は“配慮の必要性”の説明材料に。
申請前チェック
初診日の証明はそろった? 納付要件は満たす?(直近1年未納なし or 2/3) 診断書に就労の配慮・欠勤・具体的困難が入った? 申立書と矛盾なし?(同じ尺度で記載) どの等級ターゲットか腹落ちした?
よくある質問(FAQ)
Q. 週5フルタイムでも可能性はありますか?
A. 配慮・欠勤が少なく高いパフォーマンスを安定維持していると不利。短時間化や配慮の実態が鍵です。
Q. 在宅勤務なら有利?
A. 形式ではなく必要な配慮がある事実を示せるかが重要。独力で高難度業務を長時間こなしているなら不利。
Q. 会社に何を伝える?
A. 医療情報は不要。**勤務実態(時間・配慮・欠勤)**の確認に限定するのが無難です。
Q. 申請のベストタイミングは?
A. 症状が安定して“状態像”を説明できる時点。認定日請求の可否は個別に検討。
相談の流れ(こもれび社労士事務所)
初回60分で可否と方針を整理(オンライン可) 初診日・納付要件の確認、必要書類の洗い出し 診断書のポイントと就労状況の整理メモを作成 申請書類の作成・提出サポート/結果フォロー
ここまで読んで、まだ迷っていても大丈夫です。

ご相談・サービス案内
個人のご相談(労災・障害年金)/企業さまのご相談(労務DX・就業規則など)
どちらも、LINE・メール・オンラインで承っています。